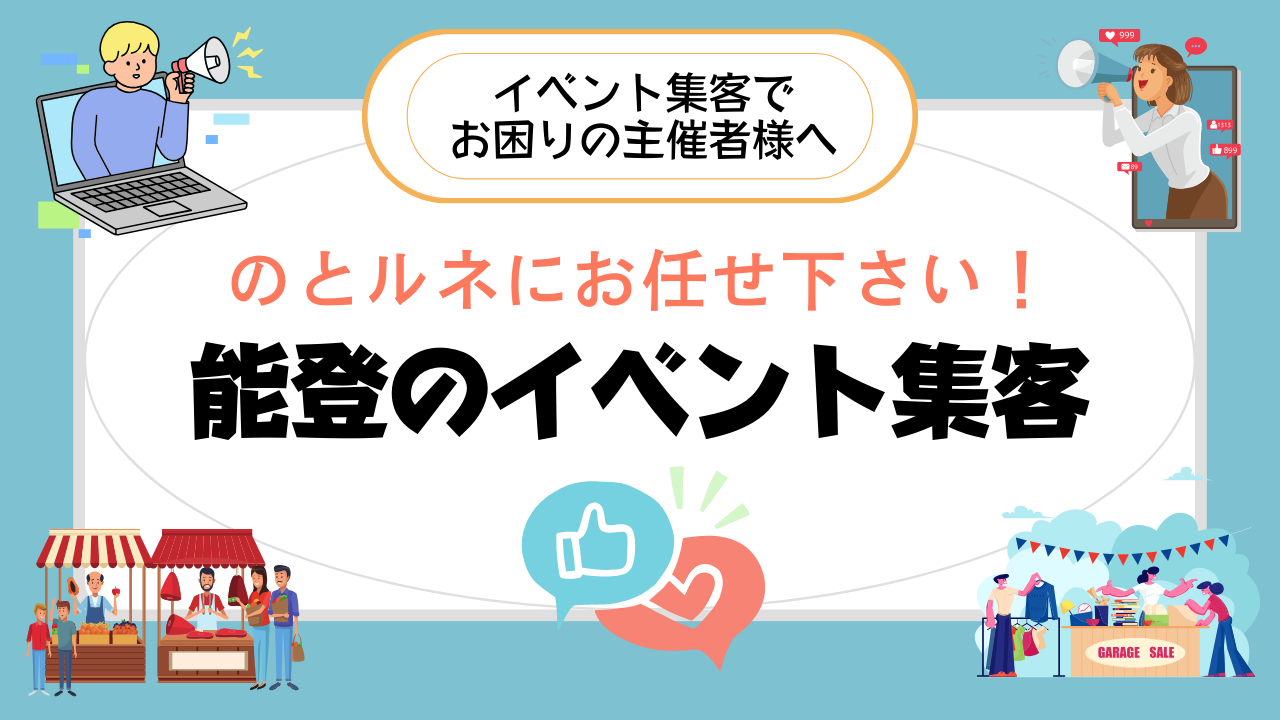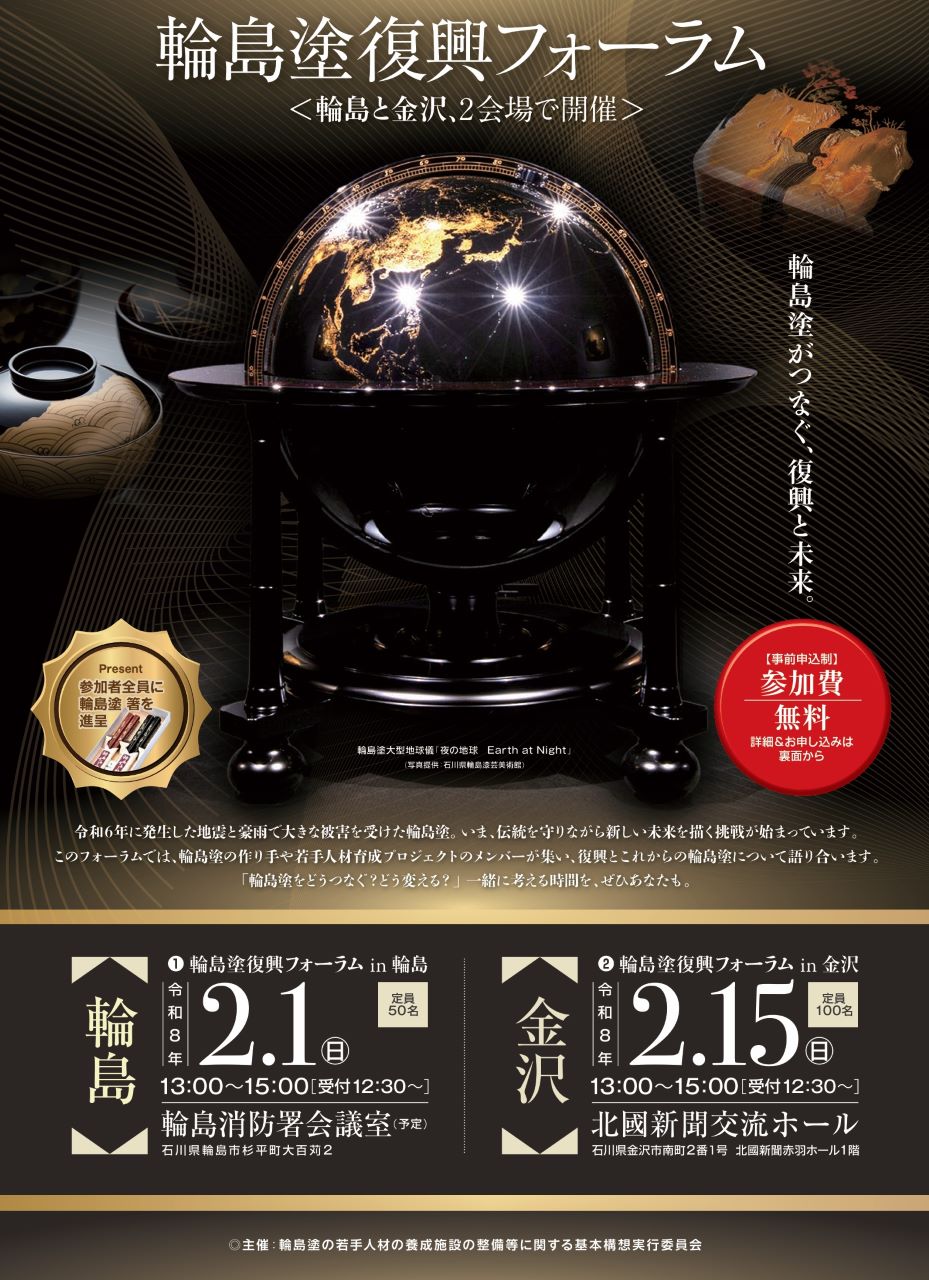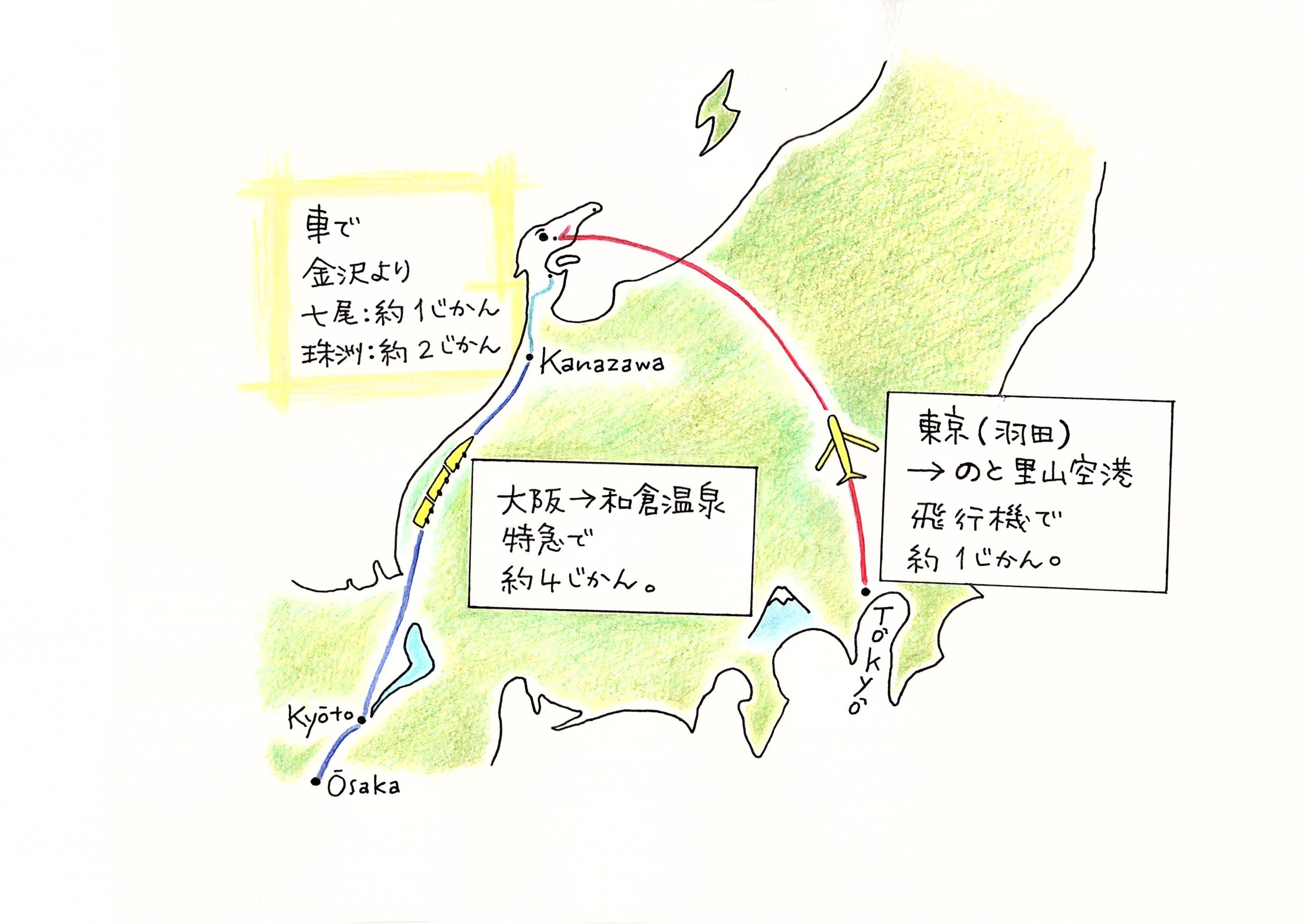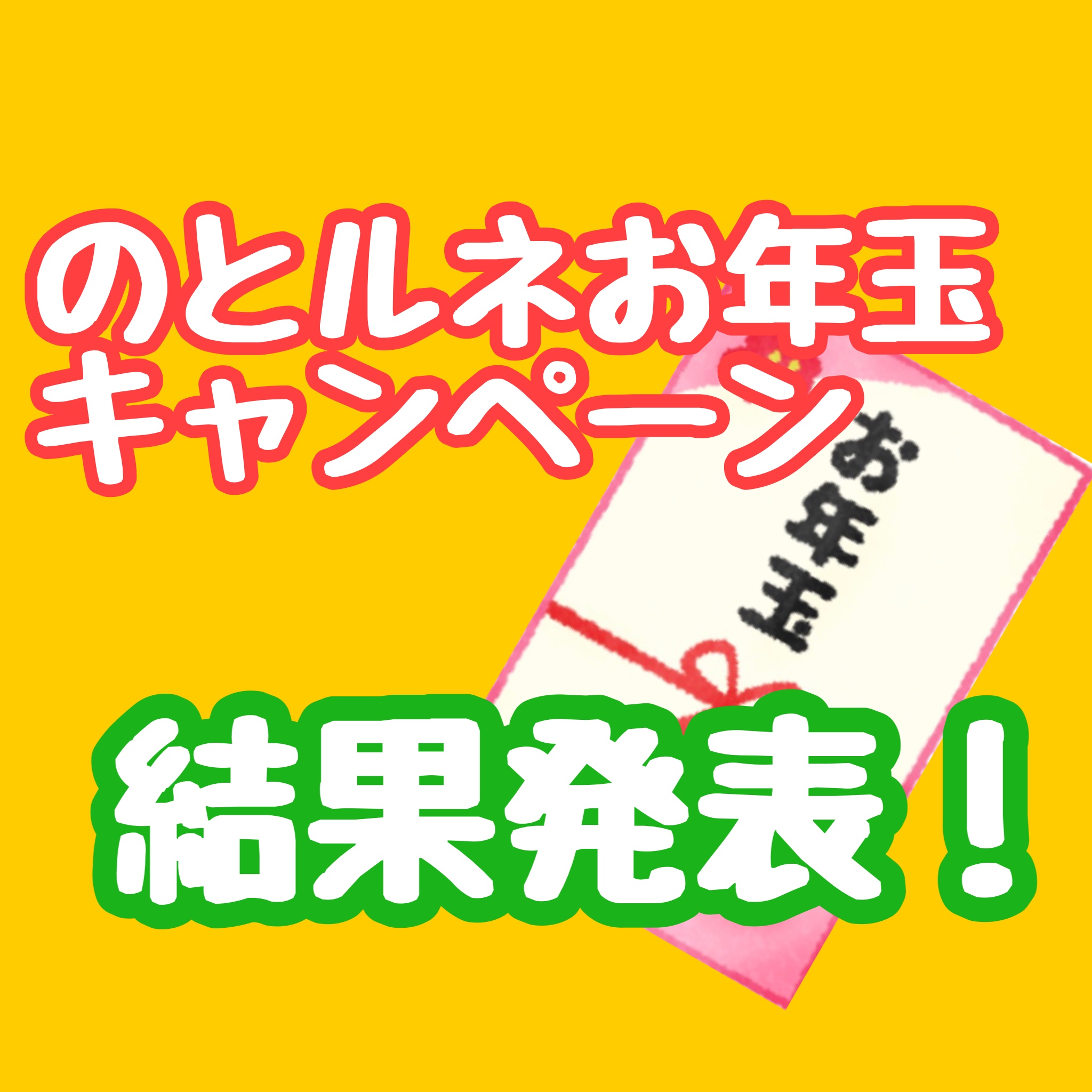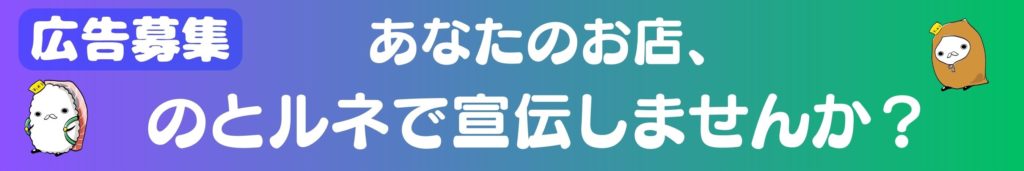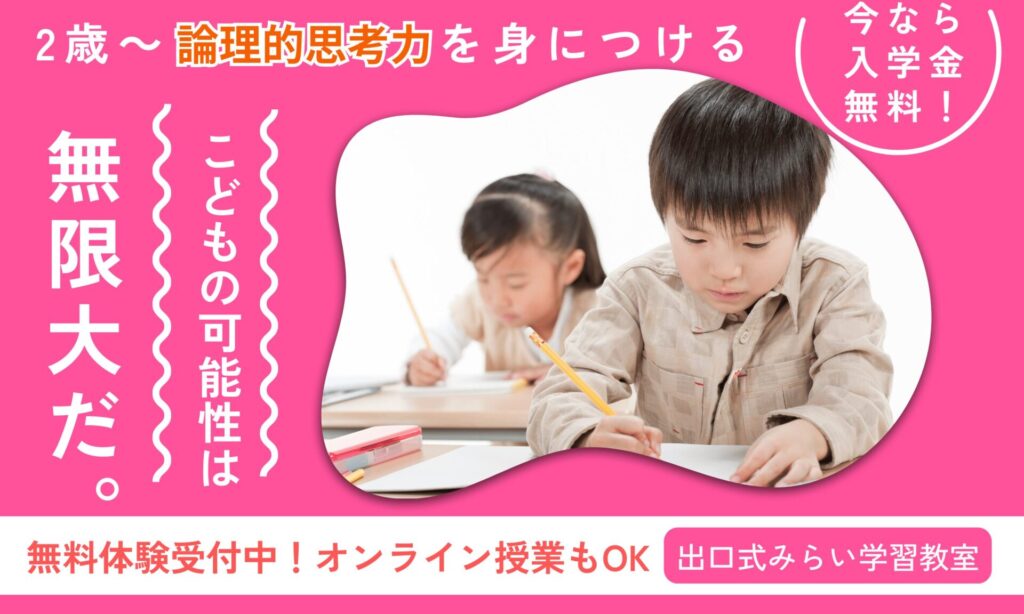能登地域では最大規模のお祭りである青柏祭(せいはくさい)は、日本一大きい「でか山」の曳きだしがあります。
青柏祭は国指定重要無形文化財・ユネスコ無形文化遺産に登録されている大変伝統ある祭礼です。
青柏祭について、でか山について語らせていただこうと思います!
令和6年能登半島地震を経て、その年はやむなく中止となりましたが、
2025年は運行されることになりました。
運行の予定が詳しくわかりましたので情報掲載いたします。
記事中の写真協力:鍛冶町出身 古川由美子様
その他たくさんの方から写真をいただきました。迫力ある写真をありがとうございました!
Contents
通称・でか山 正式名称・青柏祭

七尾市で5月3・4・5日に行われる青柏祭(せいはくさい)。
青柏祭、という名称は七尾市山王町にある大地主神社(おおとこぬしじんじゃ)のお祭りで、神饌(しんせん・お供え物のこと)を青い柏の葉に盛ることからきています。
ちなみに大地主神社は、山王(さんのう)神社と呼ばれることが多いです。
地元では青柏祭そのものを通称「でか山」と呼ぶことが多いと思います。
青柏祭は、七尾市内にある3つの町から見た目の通りの「でかい」山車(だし)が大地主神社に奉納され祭礼が行われます。
その大きさは高さ12m、重さ20t、車輪直径2mという日本一の大きさです。
でかい山、で「でか山」、と呼ばれています。
電気が通り、電柱・電線が通る前は最大18mもの大きさがあったそうです!
遠くからでも見えたそうです。

↑こちらは組み立て途中のでか山の車輪です。直径約2mはこんな大きさです!
青柏祭(せいはくさい)とは

青柏祭の起源は古く、平安時代までさかのぼります。
当時は能登という国があり、981年に能登国の祭りと定められたことからと言われています。
山車と呼ばれる曳山をひくようになったのは室町時代と言われています。
現在の青柏祭はGWに行われていますが、古くは4月の申の日に行われていました。
この申の日に行われるようになったのはここ七尾に残る「猿鬼退治」の話が元となっているようです。
青柏祭の伝説「猿鬼退治」の話
昔、七尾の山王神社(現在の大地主神社(おおとこぬしじんじゃ))へ毎年の習わしで、美しい娘を人身御供に差し出していました。
ある年、自分の娘が人身御供と決まった父親が、娘の命を助けたいあまりに神社に忍び込み、娘を喰うという何者かの話し声を聴き、その宿敵が越後にいる「しゅけん」だという事を知ります。
父親はその「しゅけん」を訪ね、事の次第を説明し、助けを求めました。しゅけんは白い毛の狼でした。
しゅけんは、かつて、人々に害を与えた三匹の猿を退治しようとしたが、一匹だけ仕留めそこなったと語りました。
そして、逃がした一匹が能登にいるならと、直ぐに七尾に駆けつけ、娘の身代わりに唐びつに入り神前に供えられました。
その夜、社殿では猿としゅけんの死闘が繰り広げられ、翌朝、相討ちとなったふたつの骸が見つけられました。
人々は、しゅけんを、手厚く葬り、また猿のたたりを恐れて、三匹の猿に見立てた山車を山王神社に奉納するようになったそうです。
こういった伝説があることから、祭礼は四月の申の日に執り行われていたようです。
「でか山」基礎知識 町の紋
でか山について、まずは基礎知識を。
でか山は、3台曳き出されます。
でか山を持っている町は、
鍛冶町(かじまち)
府中町(ふちゅうまち)
魚町(うおまち)
の3つの町です。
でか山の町の紋がそれぞれにあります。
●鍜冶町 丸に山の字

●府中町 右三つ巴

●魚町 丸に二引き

と、なっています。でか山にはこの紋が大きく掲げられているので遠目でみてもどこの町のでか山か、というのがすぐにわかります。
「でか山」基礎知識 運行日程
でか山は、毎年5月3・4・5日に行われます。
(明治時代までは4月の申の日に行われており、その後5月中旬に変更されました。そして平成2年より現在の日で行われるようになりました。)
各町のでか山の運行日程は毎年ほぼ同じです。
運行表は、七尾市・青柏祭でか山保存会様のホームページより抜粋させていただきました。
下記は、2023年5月3日夜の実際の運行の様子です。まずは動画でその迫力をご覧下さい。
青柏祭に係る各山町運行時間 2025年(令和7年度)
※【〇〇山】と表記してあるものについては後程説明記述あります。
【鍛冶町】
・5月1日
20:00 大地主神社境内~鍛冶町、三差路曳出し(試運行)
23:00 鍛冶町三差路着(見附)
・5月2日
08:00 飾り付け(鍛冶町三差路)
・5月3日
21:00 鍛冶町三差路祭礼【宵山】
21:30 鍛冶町三差路曳出し(花火合図)
23:30 大地主神社境内着
・5月4日
16:00 大地主神社境内曳出し【送り山】
19:30 鍛冶町三差路着(瀬川薬局前)
・5月5日
07:30 鍛冶町三差路曳出し【裏山】
10:30 御祓川仙対橋着(御祓川大通り巡行)
11:30 能登食祭市場前着(臨港道路)
12:20 能登食祭市場前曳出し
12:40 臨海道路通行止め解除
12:45 七尾駅北交差点着
13:10 七尾駅北交差点曳出し
13:20 御祓川仙対橋(曳回し)
13:30 御祓川仙対橋曳出し
14:00 魚町見附着
14:40 魚町見附曳出し
15:10 御祓川仙対橋着
15:30 御祓川仙対橋曳出し
20:30 鍛冶町三差路着(見附)
21:30 鍛冶町三差路曳出し
23:30 大地主神社境内着【納め山】
【府中町】
・5月1日
19:00 印鑰神社~大手町角、曳き出し(試運行)
20:00 印鑰神社前着
・5月2日
08:00 飾り付け(印鑰神社前)
・5月4日
00:00 印鑰神社祭礼
01:00 印鑰神社境内曳出し(花火合図)【朝山】
07:00 大地主神社境内着
15:30 大地主神社境内曳出し【戻り山】
19:30 大手町角着(夜見せ)
・5月5日
09:30 大手町角曳出し【裏山】
09:45 御祓川仙対橋着(御祓川大通り巡行)
10:00 能登食祭市場前着
10:30 稚児奉幣持ち神事(でか山前)
12:10 能登食祭市場前曳出し
12:40 七尾駅北交差点着
13:50 七尾駅北交差点曳出し
14:20 御祓川仙対橋「はるなお駐車場」前着
16:20 「はるなお駐車場」前曳出し・大梃子(辻回し)←見所です!!
17:50 魚町見附着
18:10 魚町見附曳出し
19:00 木槍道中唄~仙対橋通過
19:20 大手町角着
21:00 大手町角曳出し【女山】
23:00 印鑰神社境内着
【魚町】
・5月2日
15:00 御祓地区コミュニティセンター~一本杉公園入口(試運行)
17:00 御祓地区コミュニティセンター前
・5月3日
08:00 飾り付け(御祓地区コミュニティセンター)
19:00 お籠もり(気多本宮神社)
・5月4日
07:00 (花火合図)
07:10 魚町見附祭礼
08:00 魚町見附曳出し(花火合図)【本山】
12:30 大地主神社境内着
14:00 大地主神社境内曳出し【戻り山】
18:15 一本杉通り仮設商店街交差点着
18:40 一本杉通り仮設商店街交差点曳出し
19:00 魚町見附着
・5月5日
09:00 魚町見附曳出し【裏山】
09:30 御祓川仙対橋着(御祓川大通り巡行)
11:15 能登食祭市場前着(臨港道路)着
12:00 能登食祭市場前曳出し
12:35 パトリア・ミナクル前着
14:30 パトリア・ミナクル前曳出し
14:45 御祓川仙対橋着・「しるべ蔵」前着
15:40 「しるべ蔵」前曳出し・大梃子(辻回し)←見所です!!
17:40 松本町着
20:00 松本町曳出し
22:00 御祓地区コミュニティセンター曳入れ
「でか山」三台揃うのは?
各町から曳き出され、運行されるでか山ですが、三町のでか山が揃う時間と場所があります。
以下の通りです。
・5月4日12:30~14:00 大地主神社(山王神社)前
・5月5日11:30~12:00 能登食祭市場前
・5月5日12:45~13:10 七尾駅北交差点前
・5月5日14:50~15:30 御祓川仙対橋「しるべ蔵」前
三台揃ったでか山は、大迫力ですよ!
「でか山」の運行ルートは?
でか山は、各町で組み立てられ、祭事当日に大地主神社で神事をするために、大地主神社へ向かいます。
神事が終わると各町で帰っていきます。
あの大きなでか山が、町を越えて動くのです!
ちなみに大地主神社から一番遠い町は魚町です。
各町から曳きだされたでか山は、大地主神社で神事を行うために向い、
神事の後には七尾市街中心部で三台勢ぞろいの見せ場が設けられています。
でか山のリアルタイム情報がわかるアプリが登場
それぞれの町のでか山が今どこにいるのか?地図上で現在地を把握できるアプリが公開されました!駐車場とトイレの位置も分かります。ぜひ、このアプリを使ってでか山を満喫してください!
「でか山」基礎知識 ●●山とは?
でか山には、「うら山」「よい山」「朝山」「むしろ山」など、違うでか山なのか?というほど「●●山」と呼ばれるものがあります。
一つ一つ解説していきましょう。
●むしろ山(筵山)

でか山は、青柏祭が近づくと各町ででか山が作られ始めます。
作っている工程は隠されることなく、誰でも見ることができます。
まず、骨組みがなされ、その骨組みにむしろを張った状態で、試運転がされます。
試運転することにより綱のゆるみがないか、歪みはないかなどの具合を見、綱の締め直しが行われます。
ちなみに綱は、基本的には藤ツルを編んだものが使われます。乾燥したツルではなく、その時に採れたものだそうですよ!
しかし昨今は採取が難しいと聞きました。現在は幾種類かの綱が使われるそうです。
でか山はとても大きいのですが、動いている姿をみるとしなやかで弾力性のある動きです。
そんな動きをチェックする、とても大事な「むしろ山」です。
・5月1日・・・鍛冶町・府中町
・5月2日・・・魚町
●よい山(宵山)

宵山は、字のとおり、夜のでか山です。
どのデカ山よりも一番早くに動き出す鍛冶町のデカ山のことを言います。
5月3日の午後9時30分、鍛冶町の三叉路にて大地主神社による神事が行われ、そこから大地主神社まで曳きます。
・5月3日 21:30 ・・・鍛冶町
●あさ山(朝山)

こちらも、字のとおり、朝のでか山です。
朝、と言っても実は日付が変わってすぐの時間です。
こちらは府中町のでか山です。
府中町のでか山は4日午前0時に府中町の神社である印鑰(いんにゃく)神社で神事が行われその後午前1時過ぎに大地主神社へ向けて曳きだされます。
真夜中の空に響く木遣り歌、動き出すでか山。その興奮は言葉にできません!
夜中にでか山を曳くために大勢の方が集まります。
そして、午前7時頃に大地主神社に到着します。
・5月4日 1:00・・・府中町
●ほん山(本山)

ほんやま、と呼びます。
でか山で一番遠い町の「魚町」のでか山が大地主神社にむかって曳きだされるのを「本山」といいます。
5月4日の朝から曳きだされ、正午には大地主神社へ到着します。短い時間で長い距離を曳くのでその気迫と勢いはものすごいのです!
・5月4日 8:00・・・魚町
●もどり山(戻り山)

大地主神社で本祭である神事を行った後、三台のでか山は七尾市街中心部に集合するために魚町・府中町から順に曳きだされていきます。
・5月4日本祭神事の後・・・魚町・府中町
●おくり山(送り山)
大地主神社で本祭である神事を行った後、三台のでか山は七尾市街中心部に集合するために魚町・府中町から順に曳きだされていきます。
鍛冶町のでか山は最後に曳きだされていくため魚町・府中町を見送る形になるため、「送り山」と呼ばれます。
厳密にいえば、魚町のでか山を見送ってから府中町のでか山が曳きだされるので、府中町のでか山も「送り山」といいます。
・5月4日本祭神事の後・・・府中町・鍛冶町
●うら山(裏山)
5月4日に三台揃い、大地主神社で行われる神事のあと、5日はすべての山が「裏山」となります。
・5月5日・・・すべてのデカ山
●おんな山(おんなやま)
5月5日の府中町のでか山のラストランをこう呼ぶのだそうです。
でか山は元々男性が活躍するお祭りというイメージですが、実は女性も家ではおもてなしのご馳走・通称「ごっつぉ」作りで活躍しています。そんな女性もでか山最後の運行の時には女性にも楽しんでほしい、といったいわれがあるのだそうです。粋なはからいですね!
・5月5日 21:30・・・府中町
各町のでか山を連続してみる!?5月3日夜から4日朝
でか山ファンは、5月3日午後9時の鍛治町の「宵山」の後、
そのまま府中町の印鑰(いんにゃく)神社へ向かい、5月4日午前1時の「朝山」に参加します。
朝山は午前7時頃に大地主神社に到着し、次は8時から曳き出される魚町の「本山」を見に行く・・・
と夜通しのハシゴをする熱烈なファンもいます。
地元の方や、地元出身者が多いようですね。

でか山の組み立て風景
4月頃になると、鍛冶町、府中町、魚町のそれぞれ決まった場所ででか山の組み立てが始まります。
鍛冶町でか山・・・大地主神社(七尾市山王町1-13)
府中町でか山・・・印鑰(いんにゃく)神社(七尾市府中町223)
魚町でか山・・・御祓地区コミュニティセンター(七尾市一本杉町124番地)
4月にこの場所を訪れると、組み立て中のでか山の姿を見ることができますよ!
その造りは伝統ある方法をとっており、代々地域に受け継がれています。

↑4月初旬、大地主神社で組み立てが始まった鍛冶町のでか山です。

↑4月初旬、組み立て途中の府中町のでか山です!
人形見・人形宿

でか山は、大きいだけではなく、その上に飾られる舞台のストーリーや人形も必見です。
でか山の上に飾られている舞台は、芝居の場面にちなんでおり、でか山3台とも違う舞台です。
その舞台で飾られる人形は、「人形見(にんぎょうみ)」として、きめられた「人形宿」にてお披露目されます。
人形宿は各町で人形1体につき1軒選ばれ、5月2日朝頃から人形を飾るための舞台設定を行います。
家の中に庭を設えたり、花が活けられたりと工夫されて人形を惹きたてて飾ります。
5月2日夜には各町の人形宿にてお披露目となり、自由に見物することができます。
でか山に上がる前の人形を、間近で見ることができますよ。
一晩のお披露目ののち、人形はでか山という大舞台に上がります。
2025年 青柏祭 人形見・人形宿
2025年青柏祭の舞台、人形についてご紹介します。
七尾市・青柏祭でか山保存会様のホームページより抜粋させていただきました。
人形は5月2日夕刻よりお披露目されます。お披露目される人形は一体一体別の宿となりますので、
2日の夕刻より各町内は人形宿を巡る人で賑やかになりますよ。
【鍛冶町】
平安京一条院歌会の場
紫式部・一条天皇・藤原道長
「お前の書いた物語のおかげだ。 あらためて礼を言う」
宴のさなか、 藤原道長は紫式部にそっと語りかけた――。
平安中期、 一条天皇の御代。 都は大水と地震に立て続けに見舞われ た。死者は千人を超えた。 帝の行いが天変地異をもたらしたと神託が あった。一度は仏門に入った后・中宮定子を帝は呼び戻して寵愛してい た。 これが神の怒りをかったのだという。 内裏を清めるために左大臣・藤 原道長は愛娘の彰子を中宮にする。 必ずしも権勢欲からだけではなかっ た。 史上初めて一帝に二人の后が立った。 当の帝はなかなか彰子のもと を訪れない。 彰子のそばで帝を惹きつける物語を書くよう道長は紫式部 に依頼した。紫式部の 『源氏物語』 は宮中で大きな評判を呼んだ。帝は 彰子のもとへ通いはじめる。 寛弘5年 (1008) 、 彰子は待望の皇子を産ん だ。皇子誕生を祝う宴は母子が実家から一条院へ戻っても続けられた。 公卿らはこぞって寿ぎの歌を披露した。
●人形当番宅
紫式部・・・神明町/ミナ.クル
一条天皇・・・山王町/大地主神社山王閣
藤原道長・・・湊町/湊町1丁目会館
【府中町】
清須城普請場
織田信長 木下藤吉郎・前田犬千代
「天災のあとは、いかに早くもとへ戻すかが肝心にございます」
木下藤吉郎は主君・織田信長へ懸命に訴えた――。
永禄初年、 織田信長は尾張の支配を固めつつあった。 その夏、居城と する清須城が暴風雨に襲われた。 城の石垣は約百間 (180m) もの長さに 渡って崩れ落ちた。 東からは上洛を狙う今川義元の大軍が迫りつつあ る。 城の修繕は一刻の猶予もなかった。工事は普請奉行が担う。 二十日 経っても遅々として進まない。 位の低い木下藤吉郎が遅れを批判した。た しなめた信長に自分なら三日で完成させてみせると言い切る。 信長は藤 吉郎に任せる。 藤吉郎には自分なりの策があった。 盟友・前田犬千代 (の ちの利家) に協力をあおいで実行に移した。 工事箇所を一定の長さに区 切る。職人を等分してそれぞれ受け持たせる。 賞金をちらつかせて競争さ せる。 思惑どおり職人たちは二日あまりで工事を終えた。 永禄3年 (1560) 清須城を打って出た信長は桶狭間で今川軍を破った。
●人形当番宅
織田信長・・・府中町/吉田 裕志
木下藤吉郎・・・檜物町/のと共栄信用金庫
前田犬千代・・・府中町/印鑰神社社務所
【魚町】
小丸山城入城の場
前田利家 お松の方長連龍
「この城から、 能登の国をいっそう栄えさせてみせようぞ」
真新しい城に入った前田利家は正室・お松の方を前に誓った――。
天正5年(1577) 、 難攻不落といわれた七尾城は上杉謙信に攻め落と された。城主畠山家の家臣による寝返りが決め手となった。 反乱によっ て重臣・長一族は次々謀殺された。 生き残った長連龍は織田信長に助け を求めた。 信長の家臣・前田利家とともに連龍は各地で戦いを重ねる。 落城から四年後、 七尾城はついに信長に明け渡された。 連龍は悲願で あった一族の仇討ちを果たした。 信長は利家に能登一国を与える。三万 石余の越前一城主から二十三万石の国持大名へ。 破格の出世といってよ い。山頂にあって不便な七尾城を利家は廃した。 新たにふもとの小丸山 に城を築く。 港からも近い小丸山城は治世、 経済の面で利が大きかっ た。 能登は新時代を迎える。 信長の死後、 連龍は利家の家臣となった。以 後、 長家は代々前田家に仕えて加賀百万石を支えた。
●人形当番宅
前田利家・・・一本杉町/ 岡田翔太郎建築デザイン事務所
お松の方・・・魚町/小川 繁夫
長連龍・・・馬出町 寄合い処みそぎ
人形宿の様子

↑2022年のものですが、鍛冶町の人形宿となった三村様宅の様子です。
たいていは人形見当日の朝から舞台セットするのですが、三村様は少し早めに準備を行っていましたので、特別に撮影させていただきました。
人形見のために様々な格式ある品が用意されています。すごいですね!
当日は幕が張られ、立派な人形が立ちますよ!

こちらはしきりにする竹柵。
竹を切ってきて、洗って磨いて「男結び」という結び方で組み立てたそうです。
人形見について、2022年のレポートをしました。
↓↓↓
地元民に聞く!でか山の見どころ
さて、でか山が行われる七尾市。
でか山のある町は「山町(やまちょう)」と呼ばれています。
その山町に住む地元民のでか山愛は老若男女問わず、とても深いものです。
山町で生まれ育った人々がオススメする見どころと言えば!
★府中町の山が印鑰(いんにゃく)神社に戻るところ★
境内に入って、ギリギリまで引っ張ります^ ^
★大梃子・辻回し(90度の方向転換)★
若い衆が大梃子に乗って山を浮かせます。
見物人がよく見るところです♪
他にも、でか山を動かす人たちの動きは必見です!


★狭い路地ギリギリに、大地主神社に向かっているところ★
このスリルはたまりません。
★朝7時くらいに大地主神社に到着して、七尾まだら踊ります。
七尾まだらとは、七尾市を中心に遺存する祝儀歌です。

★でか山が通るルートに赤いランプ★
この赤いランプが灯ると、「山やな(^^♪」と子どもの頃からワクワクしていました
でか山の通るルートには赤いランプが灯されます。電信柱に灯ります。
![]()
★やっぱり朝山★
真っ暗な深夜に何百人って人が集まって、山が一気に動くのは、毎年ワクワクしていました。
油の匂いも、地面に残る油の染みも……血が騒ぎます。
★むしろ山★
1日に鍛治町・府中町、2日に魚町が試運転として、大手町まで動きます。
人形は2日に人形見があるので、むしろ山が終わってから乗せます。

★本祭★
4日に三町のでか山が大地主神社に納められ、正午に行われる神事です。
この神事が本来の青柏祭です。
五穀豊穣を願う神事です。

★木遣り唄★
でか山には欠かせない、木遣り衆による伸びのある声!
一度聞くと耳に残ります。
木遣りの唄がないと、でか山は曳きだされません。
長年受け継がれている木遣り唄。
小さい頃から受け継ぎはじめ、子供でも立派にうたいあげることができます。

★安全係の5人衆
こちらは2019年の魚町のでか山の安全係5人衆です。
なんといっても魅力はでか山のために動く男性のこの服装!
青柏祭という祭事の正装とも言えますね♪

でか山といえば!「長まし」
七尾銘菓・長まし(ながまし)は、ハレの日の祝い菓子で、縁起菓子です。
菓子名の語源は、「長く幸せ」という意味が込められているようです。


緑と紅に染め分けられた特徴ある形で、アンコの入ったやわらかい菓子です。
でか山を見たならば、縁起をかついでこのお菓子を是非手に取ってみて下さいね♪
ながしま、でもなく、
なまがし、でもありませんよ。言い間違えも多少聞く愛嬌ある「長まし」です。

能登最大となる青柏祭。
でか山その雄姿を是非とも実際に見ていただきたいと思います。
そして、一般客みんなで共にでか山を曳きましょう!


青柏祭について詳しく知りたい方は、和倉温泉にあるお祭り会館で本場さながらの体験・学習するこができますよ。
※しかし、令和6年能登半島地震の影響により当面の間休館しています。再開を待ち望んでいます。
お祭り会館での曳山体験の様子はこちらからもご覧いただけます。