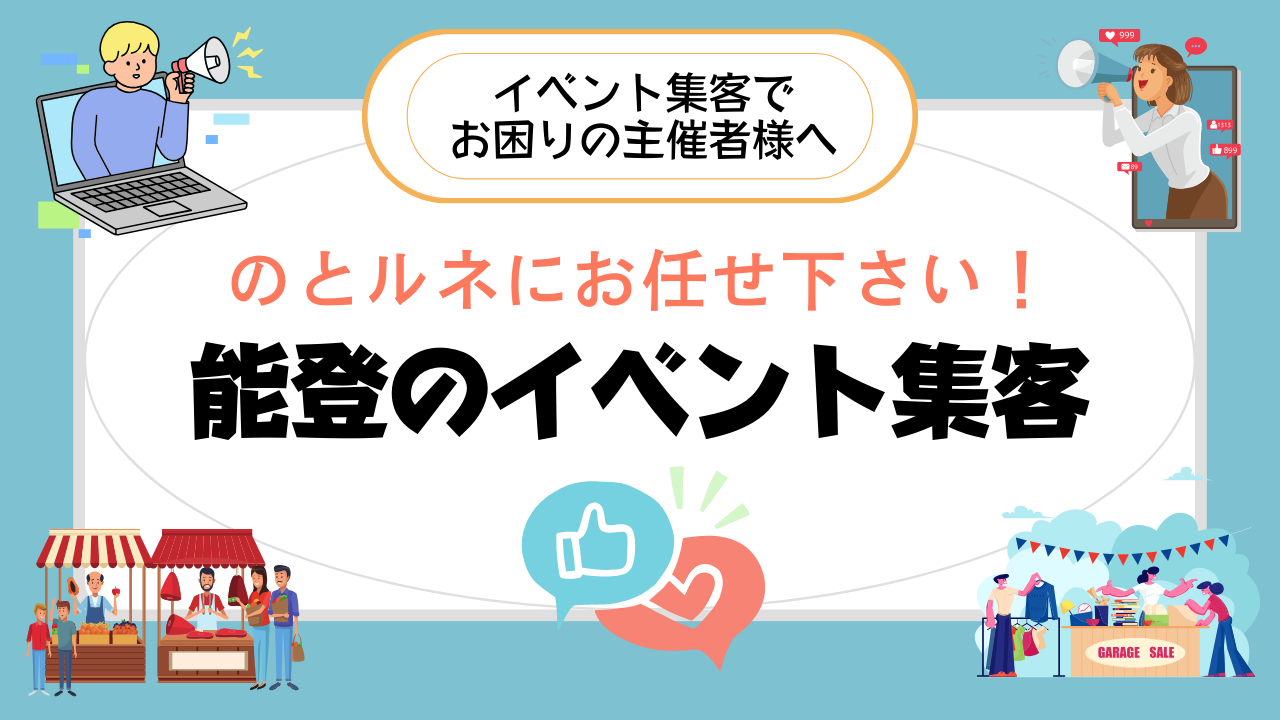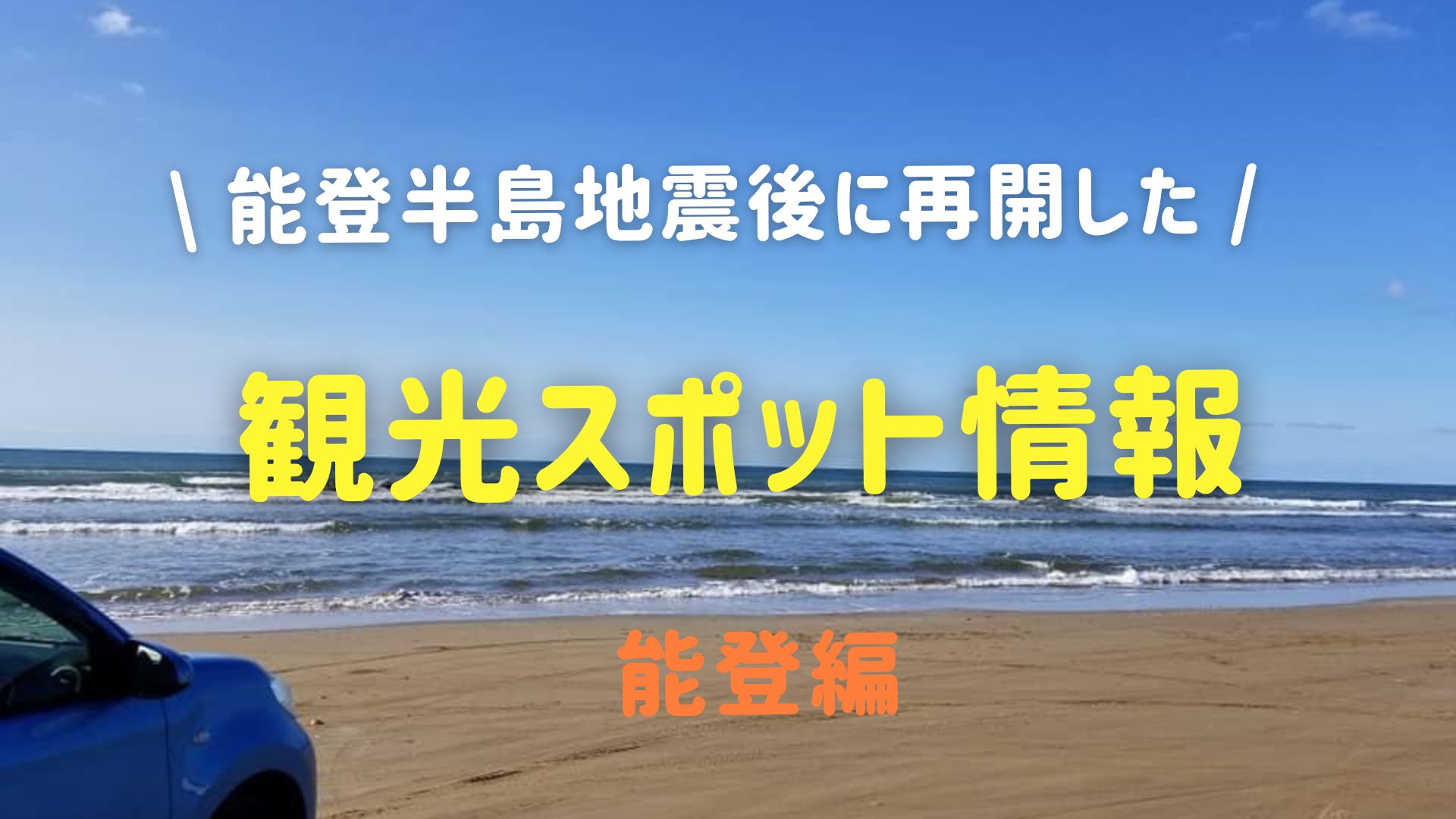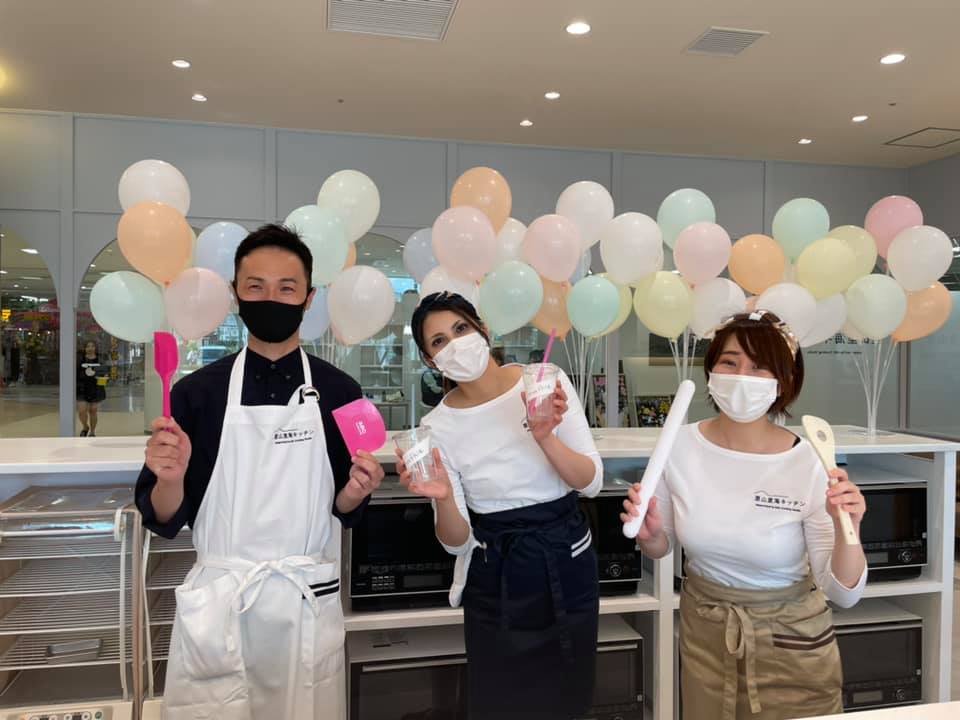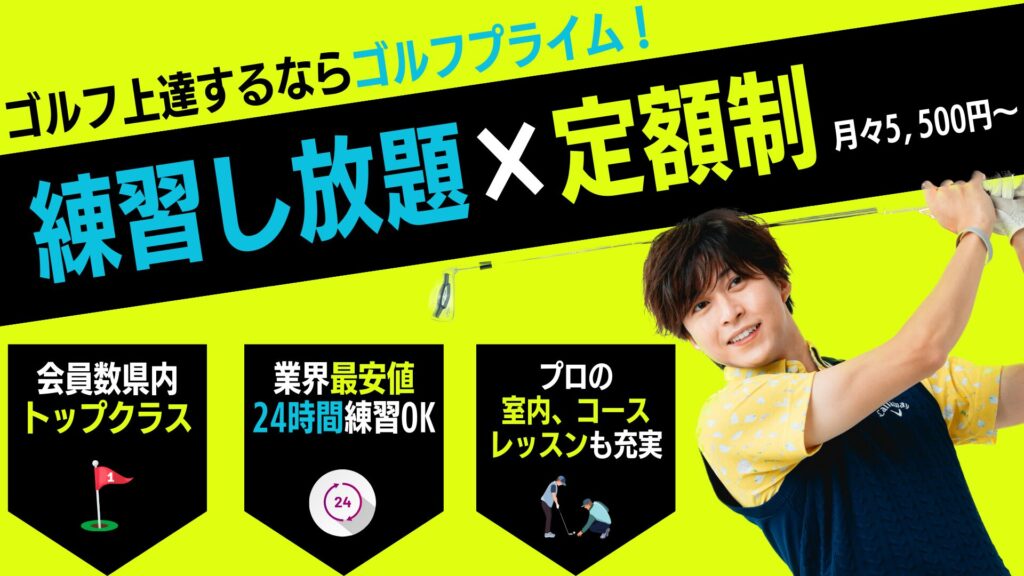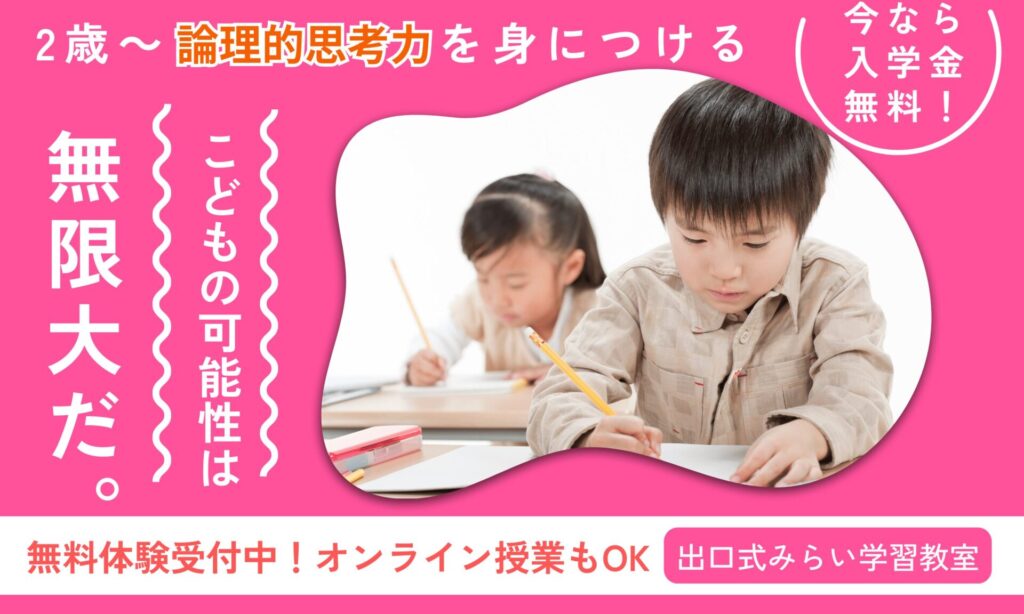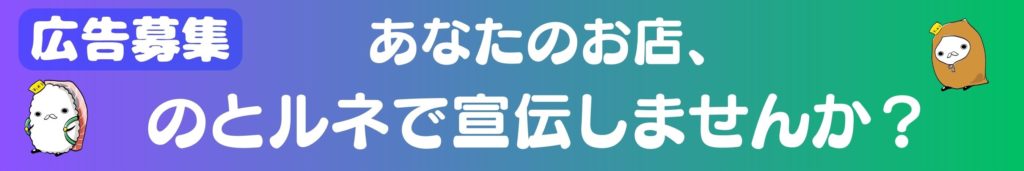のとルネアンバサダー、イベント担当るっちです!
のとルネアンバサダー、イベント担当るっちです!
2020年4月19日日曜日。七尾市の象徴ともいえる「城山」にて開山式がありました。
※2021年4月18日日曜日の開山式の様子を追加しました。
※2022年4月16日日曜日の開山式の様子を追加しました。
Contents
七尾城のあった山、通称「城山(じょうやま)」
七尾市の「七尾」の名称の由来は、七尾城のあった山(通称・城山)の7つの尾根(菊尾、亀尾、
七尾城のあった城山。七尾城は普通のお城ではなく、山城です。とても壮大です。地形をいかした屋敷がたくさんあり、その遺跡がたくさん存在しています。
貴重な遺跡であり、国の史跡にも指定されているほどです。
この日は七尾城山本丸跡にて、「開山式」が行われるため、麓から山道を歩いて登りました。
出発は、城山の麓にある「懐古館」と「七尾城史資料館」横の道からです。

案内看板もあります。毎年この時期に行われる城山トレッキングには100名以上の参加があるそうです。
2020年の今年は新型感染症の影響で中止となっています。
今回は開山式に参列するため、関係者のみで城山へ向かうこととしました。

民家の横から入っていくような道となっています。


平坦な道であれば、開山式の行われる七尾城本丸跡までの2.2kmはたやすい距離といえます。しかし、山道はたやすくありません。覚悟して進みます。

七尾城旧大手道を横切るように、能越道が架かっています。貴重な遺跡があるため、橋桁はこの地を避けて計算し建設されたそうです。


この時期は枯葉もふかふかしていて歩きやすかったと思います。しかし、勾配は次第にきつくなっていきます。

周りを見ながらゆっくり30~40分かけて七尾城本丸跡近くまでいくと、景色が開けており、七尾湾が見えます。
新型感染症が流行し、様々なことが自粛となり、気分が沈みがちでしたが、変わらぬ大自然の美しさに触れ明るい未来をイメージする力が沸いてきました。
七尾城本丸に到着すると、見事な石垣が!
多くの段がある石垣に迫力があり、圧倒されます!


2020年4月19日七尾城山開山式
七尾城本丸跡からの景色です。天気がよく、絶景です。
七尾市街、七尾湾、能登島、その向こうには遥か輪島まで見ることができます。
山桜も散り際で見事な時節でした。

七尾城本丸跡にあるお社で、神主さんが詞を捧げ、玉串を奉奠させていただきました。

点在する郭(くるわ)を辿りながら、歩みを進めます。
郭とは、屋敷や番所があったとされる平坦な地のことだそうです。
城山に慣れている方は、この景色に道を見い出します。

途中、地の利を活かした堀切(ほりきり)を見ることができました。外敵の侵入防止や遅延のために造成された塀のようなものです。七尾城の周りをここから見張りをしていたのではと思われます。
山中、所々に遺跡があり、当時の石垣も山間に垣間見ることができます。

木々にはこんなに太い藤のツルがありました。山中でも陽射しはありました。道は、明らかに猪の通った道でした。

足元、頭上に気を付けながら恐る恐る進む箇所もありました。私でも道とわかるものが見えたときは安心しました!
山の道に慣れた方は、この山の斜面でも「踵で踏みしめるように!」と駆けていきます。
こういった山中を歩けるのは3,4月が適しているそうです。熊も、蛇も、虫もいません。もう少し温かくなると冬眠から目覚め、草も生い茂り、山中を進むことは困難になるそうです。
城山展望台到着


頂上の展望台からは、なんと白馬岳が見えました。
輝く白い山々が見えるのがわかりますか?この展望台に登らないと見えないそうです。今日はお天気も良く、幸運でした。

石川県の特徴的な地形を一望できます。
無料の望遠鏡からは輪島にある能登空港の滑走路を見ることができました!

帰りも、歩いて下山します。

途中、様々な可愛らしい山野草を楽しむことができます。山野草の名まえがわかるとトレッキングは何倍も楽しいものになると思います。

かなり麓に近づいたところに、神社跡がありました。階段を登ったところの奥の宮は残されたままです。
本社は山の麓
七尾の名称の由来、七つの尾根のひとつが「竹尾」といい、尾根ひとつひとつにお社があると言われています。
こちらは「竹」の八幡神社。
ちなみに開山式が行われた本丸跡のお社は「松尾」のお社といわれているそうです。



七尾城山インター入り口の、コンビニ横の道にでました。
そこから城山を見上げると、ものすごい距離を歩いたことがわかります。

七尾城山は、山好きに、自然好きに、山草好きに、城好きに、考古学好きに、とにかく話題の宝山で、おすすめします。
運動不足になりがちな今、散歩は推奨されていますが、ソーシャルディスタンスが保てて、屋外で歩くことができ、身体と心のリフレッシュができました。
七尾の巨大山城に思い巡らせながら、来年はこの素晴らしい景色をみなさんと共有できるようにと切に願いました。
2021年4月18日七尾城山開山式
最初の開山式のレポートから、はや1年が過ぎました。
この年も、開山式に合わせて行われるトレッキングツアーは中止となっています。
新型感染症の影響のため、この年も規模を縮小しての開山式です。
2021年4月18日、厳かに神事が行われましたよ。

この日は生憎の雨でしたが、新緑は生き生きとしており、瑞々しい山の様子でした。
鳥居の上に、城山神社があり、雨の中、神事が行われていました。
2021年もトレッキングツアーは中止でしたが、個人的にトレッキングをする分には密にはなりません。
雨でしたが、城山の旧道といわれる「七尾城トレッキングコース」を行ってみました。

スタートは七尾城史資料館です。

係員さんがお見送りをしてくださいました。


七尾城トレッキングコースは、動きやすい服で、スニーカーであれば軽装で進むことができます。
道を見て、ちょっと登ってみようか?というような勢いで進む方もいらっしゃいます。
この日は雨でしたので、防寒着は必要でした。

焼き物の破片がありました。
トレッキングコースにはちょっとした遺跡が点在しています。この辺は七尾城当時ごみ捨て場だったそうです。
歩きながら、当時の物が発掘できるかもしれませんよ?!

要所要所にこうした石垣が詰まれています。
苔むしており、厳かな雰囲気があります。

トレッキング途中で見晴らしの良い場所に出ました。

約一時間かけて、本丸跡までたどりつきました。
本丸跡の大きな桜、昨年の開山式では満開でしたが、今年はすでに葉桜となり散っていました。
今年の桜は早かったようです。
2022年4月16日 七尾城山開山式
さて、城山開山式をこののとルネでレポートするのも3回目となりました!
この年もトレッキンングツアーは企画されず、かわりにクリーン大作戦と称して、城山の車道のゴミを拾いながら登る企画があり、
七尾市長を始め市民の方々の参加がありました。

午前中雨の予報にも関わらず、晴天に恵まれた開山式です。
能登島大橋もくっきりと見ることができました。

城山神社そばにある桜の木も満開を迎えておりました。
時折吹く風に桜吹雪がとても美しかったです。

城山関係者や地元の関係者を中心に、神事が行われています。

のとルネアンバサダー木戸奈諸美も、七尾市議会議員として参列しました。

七尾市の宝である城山を愛してやまない木戸奈諸美です!

【七尾城山 開山式】
2020年4月19日
2021年4月18日 七尾城本丸跡にて
2022年4月16日 七尾城本丸跡にて
●トレッキングに大人気の七尾城山はここから攻め上がれ!七尾城山登山口駐車場【七尾市】






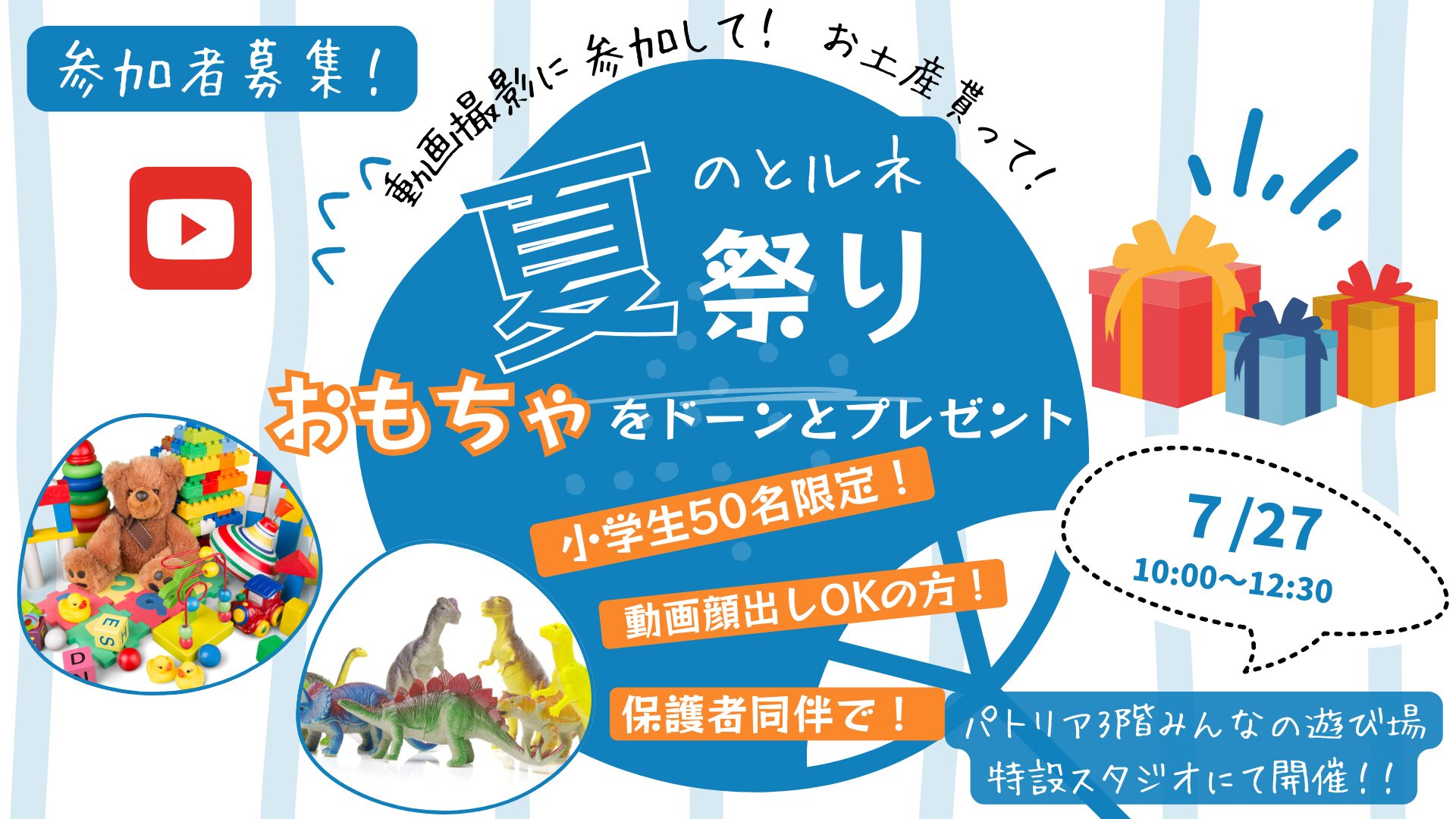

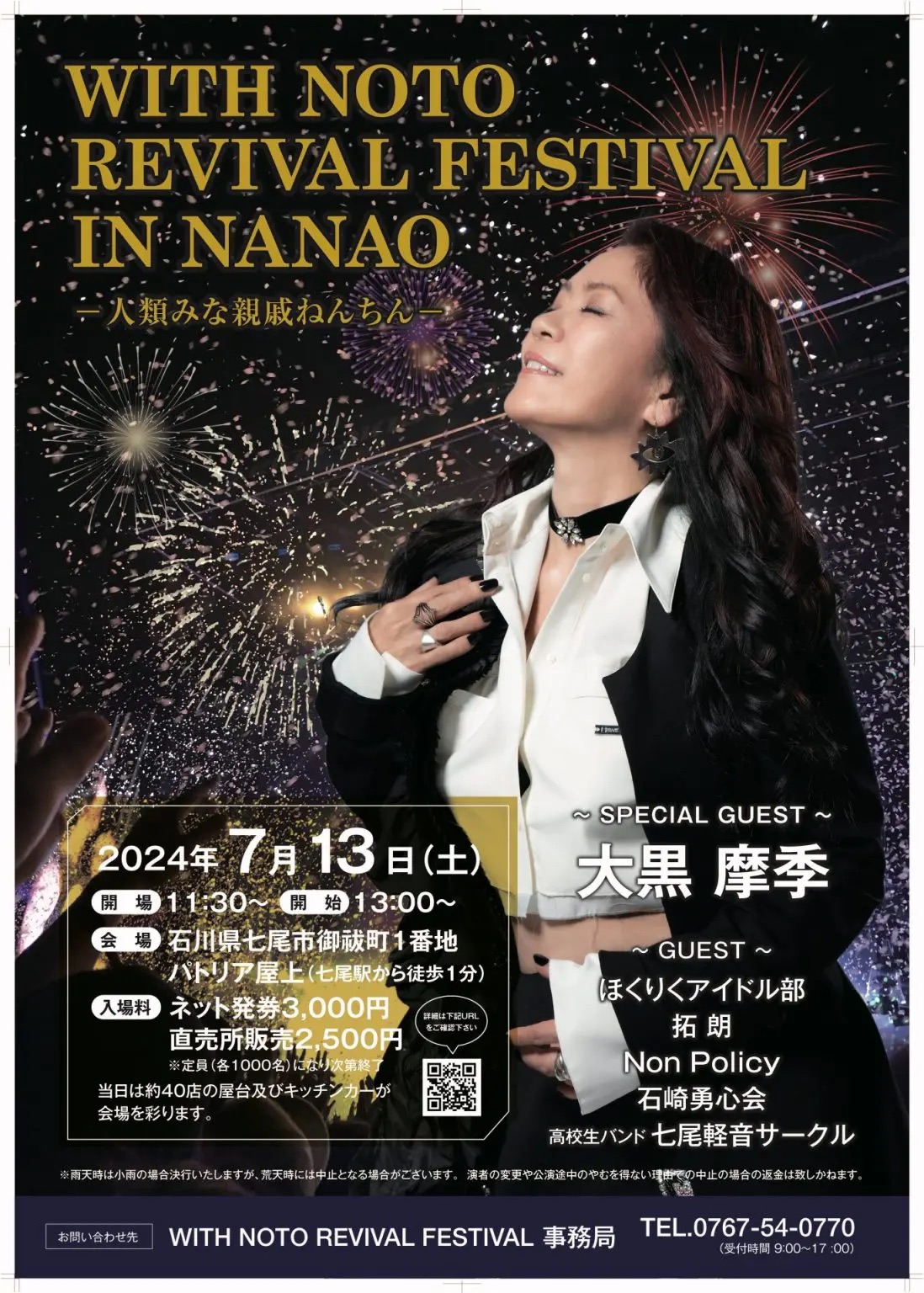




」さんへ行ってみた-定置網漁-の-漁師-体験-!-【-山崎至-】【-七尾市-】【-石川-体験-】.jpeg)
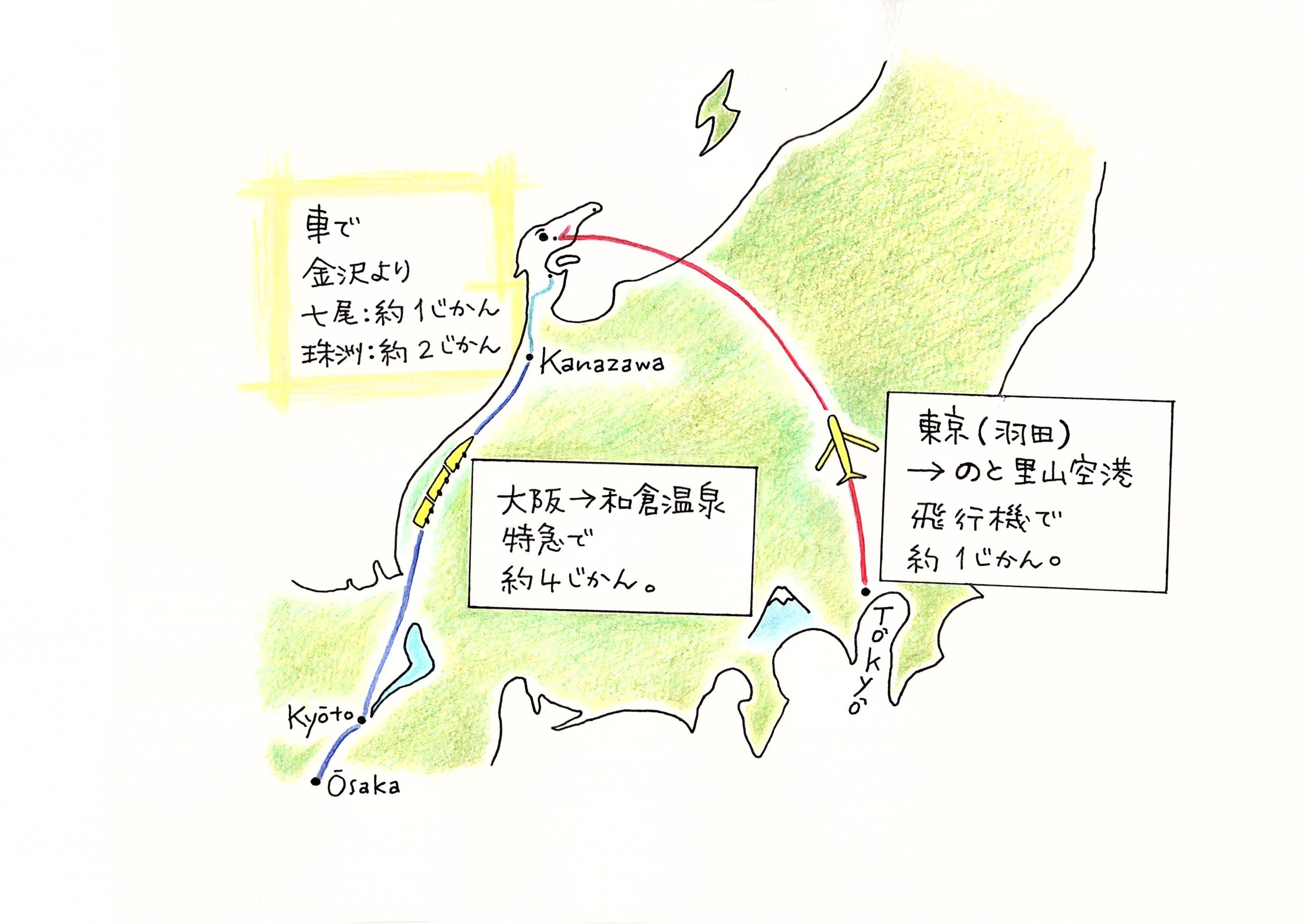

.jpg)